お祭りでつい手に入れた小さなカメ。「かわいくて連れて帰ってきたけど、どう育てればいいのかわからない……」と戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、爬虫類飼育歴20年の筆者が、初心者が最初に押さえておきたい準備と飼育のコツを、実体験を交えて丁寧に解説します。
お祭りでの出会いと持ち帰り
お祭りで出会ったカメとの再会|小さな記憶が呼び覚まされた瞬間
15年前の夏、地元のお祭りを歩いていたとき、「カメすくい」の屋台に目が止まりました。小さな水槽の中をゆっくり泳ぐカメたちの姿に、子どもの頃に飼っていたカメとの記憶がふっと蘇ったのです。
当時はまだ小さく、世話の仕方も手探りだった私ですが、それでも一緒に過ごした日々は心に残っていました。「もう一度、ちゃんと育ててみたい」――そんな思いに背中を押され、私は1匹のカメを手に取りました。
屋台の人からは「このまま持ち帰れますよ」と透明なケースを渡されましたが、真夏の暑さの中での持ち帰りは予想以上に気を使うものでした。直射日光を避け、風通しの良い場所を選びながら、カメの様子を何度も確認し、そっと家へ連れて帰りました。
自宅に着いてからはすぐにエアコンの効いた部屋にケースを置き、水温が下がるのを待ちつつ、環境づくりを始めました。
次の章では、初心者の方でも無理なく始められるよう、実体験をもとに飼育環境の整え方や必要な道具について詳しく紹介していきます。
最初の数日と飼育環境の準備

自宅にあるもので“なんとなく”スタート
カメを迎えた翌日、私はとりあえず家にあるもので飼育環境を整えようとしました。洗面器に水を張り、古い金網のトレイを斜めに入れて陸地の代わりにし、懐中電灯を日光の代わりに照らす、というかなり簡易的な方法でした。
しかし、数時間で水が濁り始め、カメは陸に登れず、水底でじっと動かなくなりました。食べ残したエサが水の中に沈み、においも気になってきました。正直、この状態で育て続けるのは無理だと感じました。
ペットショップで得た最低限の知識と道具
不安になって近所のペットショップへ行き、店員さんに相談しましました。基本的な飼育に必要な道具を丁寧に教えてもらい揃えたのが、以下の5点です:
- 60cmサイズのガラス水槽
- カメ用の浮島タイプの陸地(吸盤付き)
- 水中フィルター(静音タイプ)
- 水温を一定に保つヒーター
- 紫外線ライト(UVB照射機能つき)
すべて合わせて約15,000円。
思っていたよりも高く感じましたが、「健康に育てるために必要な最低限」と聞いて納得しました。

買い物メモのコツ:
予算はフィルター>ライト>水槽>ヒーター>陸地の優先順で検討しました。静音とメンテ性を重視するのがおすすめです。
正しい環境が整うと、カメの動きも変わった
水槽を設置し直してから数時間後、カメがゆっくりと陸地に登り、甲羅を乾かしている様子が見られるようになりました。それまでの元気のない様子と違い、体を伸ばしたり、周囲を見渡したりと、明らかに動きが変わったことに驚きました。
設備を整えることで、カメが安心して過ごせる環境を作れると実感できたのはこのときが初めてでした。
名前をつけた日と、暮らしに入り込んでくる存在感
名前をつけたことで、飼う意識が大きく変わった
水槽の設置がひと段落してから数日後、ふと思い立ってカメに名前をつけることにしました。それまでは「この子」「カメちゃん」など曖昧な呼び方をしていましたが、少しずつ存在が身近に感じられていたこともあり、自然と名前が浮かんできました。
甲羅の色が少しクリームがかっていたのと、手のひらサイズでころんと丸かったことから「くるみ」と名付けました。そう呼ぶようになってから、ただの「飼っているカメ」ではなく、「うちのくるみ」という感覚が芽生え始めたように思います。

名前をつけると… 「観察対象」から「家族」へと意識が変化し、世話が習慣化しやすくなるメリットがありました。
世話を“習慣”として続けられるようになった
くるみを迎えてから1週間ほどで、エサやりと水換えのリズムが生活の一部になりました。朝、カーテンを開けたあと水槽に近づくと、くるみが水面に顔を出すようになり、それがひとつのルーティンになっていきました。
- エサは1日1回、浮上タイプのカメフードを4〜5粒
- 水換えは週2回、底のゴミをスポイトで取り除きながら実施
- 紫外線ライトは朝7時〜夜7時まで12時間自動点灯設定
こうしたルールが整ってくると、飼育というよりも「一緒に暮らしている」という実感が強くなってきました。

小さな変化に気づけるようになった
名前を呼んだときにくるみが首を伸ばしたり、エサの時間が近づくと水中からこちらを見てきたり、そういった反応のひとつひとつに気づくようになると、「生きている実感」を感じられるようになりました。
小さな命でも、毎日見ていればその日の元気さや様子の違いに気づくことができる。それが、飼育の面白さでもあり、責任を持つきっかけにもなりました。
日常で感じた戸惑いやつまづき、工夫の積み重ね
初心者ゆえの迷いと判断ミス
くるみとの生活が少しずつ軌道に乗ってきた頃、小さな困りごとが次々と出てきました。たとえば水が想像以上に早く汚れてしまうこと。最初は週に1回の水換えで十分だと思っていましたが、エサの食べ残しや排せつ物によって、2日もしないうちににごりが目立つようになりました。
水が汚れると、くるみの動きも鈍くなることがあり、調子が悪そうに見えることも。はじめは水換えが原因なのか、エサのせいなのか、それとも光の量かと原因の切り分けに悩みました。
観察と記録で少しずつ改善できた
そこで、1週間ほど毎日の様子を簡単に記録するようにしました。「今日はよく食べた」「浮島の上で動かない時間が長かった」「水のにおいが強くなった」など、思いつくことをスマホのメモに残していくと、行動の傾向と水の状態の関係がだんだん見えてきました。
結果的に、エサの量を少し減らし、食後1時間以内に残ったフードを取り除くことで、水の汚れはかなり軽減できました。また、底に沈んだゴミは週2回の水換えに加えて、中間日にスポイトで吸い取ることで清潔を保てるようになりました。

観察日誌をつけることで改善ポイントがわかってきました。
便利だった道具と習慣
実際に役立ったのは、以下の3つです:
- 水換え専用ポンプ:バケツでの作業が格段に楽になった
- スポイト式クリーナー:食べ残しを吸い取るのに最適
- 記録アプリ(メモ帳):行動と環境の変化を見える化できた
5年目の現在と、カメとの距離感の変化
成長に合わせた環境の変化
くるみを飼い始めた頃は、手のひらにすっぽり収まるサイズでした。けれど、5年が経った今では甲長は20cm近くなり、水槽も当初の60cmから90cm、そして120cmへとサイズアップしました。設置場所もリビングの一角から、日当たりと風通しの良い窓際に移しています。
成長に合わせて必要なものも増えていきました。フィルターの性能を上げ、浮島も大型のものに交換し、冬は温度を保つためにヒーターをダブルで設置するようになりました。こうした変更は決して手間ではなく、「この子が快適に過ごせるなら」と自然に受け入れられるようになっていきました。

成長に合わせて、ケージのサイズアップやフィルター性能も良いものに変えています。
日常に組み込まれた“存在感”
毎朝カーテンを開けると、くるみが水面から顔を出すのが見えます。エサの時間が近づくと、水中から浮島の上に出てきて、じっとこちらを見てきます。そんな姿が日常の一部になり、忙しい朝でも「この子の世話だけはちゃんとしよう」という気持ちになります。
旅行の予定を立てるときも、くるみのことを考えて短期間に調整したり、信頼できる家族に世話を頼んだりしています。

飼うことで得られた意識の変化
以前は、生活の中で生き物の存在をそれほど意識することはありませんでした。でも、くるみと暮らすようになってからは、水の状態、気温、日当たりなど、自然環境にも敏感になりました。身の回りの小さな変化に目を向ける習慣ができたのは、大きな変化だったと思います。
また、続けるうちに「長く付き合うこと」の意味を少しずつ理解するようになりました。カメは、最初の一瞬ではなく、何年もかけてゆっくりと関係が深まっていく生き物だと実感しています。
カメと暮らして見えてきたこと・気づきと学び
変化に気づく“観察力”が自然と身についた
カメと生活するようになって、もっとも変わったのは「観察する習慣」が身についたことです。毎日同じように見えていたくるみの行動も、よく見ていると日によって微妙に違います。朝の動きが鈍い日は水温が下がっていたり、浮島に長くいる日は紫外線を多めに浴びようとしていたり。
こうした小さな変化に気づくようになってから、「飼育=世話」ではなく、「生活の一部」として捉えるようになりました。最初は“ちゃんとしなきゃ”という意識でいっぱいでしたが、今では無理なく続けられています。
自分のペースで関係が深まる
カメは犬や猫のように感情を表に出しません。鳴かないし、触っても反応が鈍いことが多いです。それでも、同じ時間を過ごしていく中で、「この子は今、こうしたいんだな」というのが少しずつ分かってきます。

毎日声をかけることで、名前に反応するようになり、距離が縮まってきました。
飼う側の「姿勢」が問われる生き物
カメはとても丈夫で、工夫すれば小さなスペースでも飼えます。でもその一方で、飼い主が環境管理を怠れば、急激に体調を崩すこともあります。気温、水質、照明、エサのバランス。それぞれがカメの体調に大きく関わっていることを、経験を通じて知りました。
まとめ
・まずは水槽・陸場・フィルター・ライトなど最低限の環境を整える
・水質と温度の変化にはこまめに気づけるよう、観察と記録を続ける
・成長に合わせて水槽や器具を見直し、「長く付き合う前提」で準備する
お祭りでの「かわいい!」という気持ちから始まった出会いでも、環境づくりと観察を重ねていけば、カメとの暮らしは落ち着いた楽しい時間になっていきます。迷ったときは完璧を目指しすぎず、「今できる一歩」を積み重ねていってあげてくださいね。
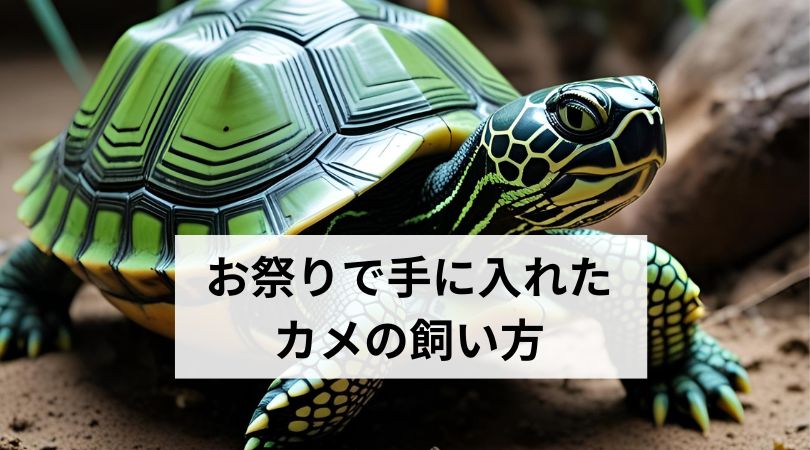
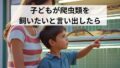

コメント